遺言書保管制度の創設
相続センター>民法改正(2018年7月成立)のポイント>遺言書保管制度の創設
遺言書保管制度の創設
2020年7月10日から遺言書の保管制度が始まりました。
一般的に使用される遺言の形式として公正証書遺言、自筆証書遺言がありますが、公正証書遺言が公証役場で保管されるのに対し、自筆証書遺言では保管の制度がありませんでした。
そのため自筆証書遺言では遺言者自身が保管するケースが多く、相続開始後に遺言が発見されない、相続人による改ざんの可能性などの問題が生じていました。
問題の解消のため法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管できる制度が開始されました。
遺言書保管制度の手続き(遺言者の手続き)
遺言書を預ける(遺言書の保管の申請)
①自筆証書遺言の作成
②保管の申請をする遺言保管所を決める
保管の申請ができる遺言書保管所は下記になります。
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言保管所
※既にほかの遺言書を預けている場合には、その遺言保管所
③申請書を作成する(申請書は法務局のサイトからダウンロードできます。)
④保管の申請の予約をする※予約は必須です。
⑤保管の申請※遺言者本人が行く必要があります。
申請に必要なもの
- 遺言書
- 申請書
- 本籍の記載のある住民票の写し等
- 本人確認書類(顔写真付きのもの)
- 手数料 収入印紙3,900円
⑥ 保管証の受け取り
預けた遺言書の確認(遺言書の閲覧)
①閲覧の請求をする遺言保管所の確認
- モニターによる閲覧は、全国のどの遺言書保管所でも請求可能です。
- 遺言書原本の閲覧は、原本が保管されている遺言書保管所でのみ請求できます。
②請求書を作成する(申請書は法務局のサイトからダウンロードできます。)
③閲覧請求の予約をする
④閲覧の請求(遺言者本人のみ)
請求に必要なもの
- 本人確認書類(顔写真付きのもの)
- 手数料 モニターによる閲覧収入印紙1,400円
原本の閲覧 収入印紙1,700円
⑤閲覧する
遺言書を返してもらう(遺言書の保管の申請の撤回)
①撤回書の作成(申請書は法務局のサイトからダウンロードできます。)
※保管の申請の撤回ができるのは遺言者本人だけです。
②撤回の予約
- 保管の申請の撤回は原本が保管されている遺言書保管所でのみできます。
③撤回・遺言の返却
- 本人確認書類(顔写真付きのもの)
住所等の変更の届出
①届出書の作成(申請書は法務局のサイトからダウンロードできます。)
- 遺言者本人、遺言者の親権者・成年後見人等の法定代理人が届出できます。
②変更の届出の予約をする
- 全国の遺言書保管所でできます。また、郵送による届出も可能です。
③変更の届出
必要なもの
- 変更が生じた事項を証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等)
- 請求人の身分証明書のコピー
- 法定代理人が届出する場合は戸籍謄本、登記事項証明書(作成後3か月以内)
遺言書保管制度の手続き(相続人等の手続き)
※相続人等の手続きは遺言者が死亡している場合に限られます。
遺言書が預けられているか確認する(遺言書保管事実証明書の交付の請求)
①請求書の作成
全国の遺言書保管所で交付申請できます。
申請できる者
- 相続人
- 遺言執行者等
- 受遺者等
上記の親権者や成年後見人等の法定代理人
②交付請求の予約
③交付の請求
添付書類
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
- 請求人の住民票の写し
- 請求人が相続人であることが確認できる書類(相続人が請求する場合)
- 登記事項証明書(後見人等が請求する場合)
- 本人確認書類
- 手数料 収入印紙800円
- 返信用封筒と切手(郵送による申請の場合)
④証明書の交付
遺言書の内容の証明を取得する(遺言書情報証明書の交付の請求)
①請求書の作成
全国の遺言書保管所で交付申請できます。
申請できる者
- 相続人
- 遺言執行者等
- 受遺者等
上記の親権者や成年後見人等の法定代理人
②交付請求の予約
③交付の請求
添付書類
- 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)
※法定相続情報一覧図の写しでも代用できます。 - 請求人の住民票の写し(受遺者、遺言執行者等が請求する場合)
- 本人確認書類
- 手数料 収入印紙1,400円
- 返信用封筒と切手(郵送による申請の場合)
④証明書の交付
相続人等が証明書の交付を受けると、そのほかの相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知が行われます。
遺言書を見る(遺言書の閲覧)
①請求書の作成
- モニターによる閲覧は、全国のどの遺言書保管所でも請求可能です。
- 遺言書原本の閲覧は、原本が保管されている遺言書保管所でのみ請求できます。
申請できる者 - 相続人
- 遺言執行者等
- 受遺者等
上記の親権者や成年後見人等の法定代理人
②閲覧請求の予約
③閲覧の請求
添付書類
- 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)
※法定相続情報一覧図の写しでも代用できます。 - 請求人の住民票の写し(受遺者、遺言執行者等が請求する場合)
- 本人確認書類
- 手数料 手数料 モニターによる閲覧収入印紙1,400円
原本の閲覧 収入印紙1,700円
④閲覧
相続人等が遺言書の閲覧をすると、そのほかの相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知が行われます。
※遺言書保管制度の手続きについてはすべて予約制です。
Q&A
Q.法務局で遺言の書き方や内容などの相談もできますか?
法務局では遺言の書き方や内容の相談には対応していません。外形的な確認のみです。
Q.保管制度を利用した遺言としていない遺言で効力に差がありますか?
保管制度を利用してもしなくても遺言の効力自体には影響はありません。
Q.保管制度開始前の日付の遺言書でも預けることはできますか?
保管の様式に合う遺言であれば利用することは可能です。
Q.代理人による申請でも可能ですか?
代理人による申請はできません。必ず遺言者本人が出頭する必要があります。
Q.写真付きの身分証明書がない場合はどうすればよいですか?
写真付きの身分証明書は必須です。ない場合はマイナンバーカードの取得等で対応することになります。
Q.保管証を紛失した場合は再発行ができますか?
保管証の再発行はできません。保管証を紛失した場合でも手続きは可能です。
Q.保管している遺言の内容を変更できますか?
保管申請の撤回をして遺言の返還を受けて、変更後の遺言で再申請することができます。また、申請を撤回せずに変更後の遺言で保管申請をすることもできます。
Q.予約せずに法務局に行って申請することはできますか?
保管の申請は原則予約制です。予約がない場合には申請できない場合があります。
Q.杉並区の住民の場合、住所地を管轄する遺言書保管所はどこの法務局ですか?
杉並区に住民票のある方が住所地を管轄する遺言書保管所に保管の申請をする場合は東京法務局本庁(千代田区九段南1-1-15)です。
私たちがサポートします!!お気軽にご相談ください。
相続税・贈与税・不動産譲渡を専門にしています。元国税職員としての税務調査経験を活かした専門性の高い正しい節税によるサポートを行います。
「大久保さんの良いところは何よりもお人柄ですね。」と言われます。国税局・税務署での税務調査経験を十二分に活かしながら、相続税の申告について皆様が本当に安心できるよう頑張ります!

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。
「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。
遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。
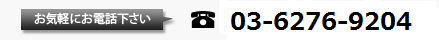
無料相談 御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

