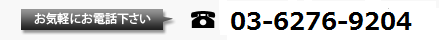寄与分とは
特定の相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をしていたときには、その相続人の相続分は貢献の度合いに応じて増加します。
これを寄与分といいます。
寄与分が認められるためには特別の寄与が必要になります。
夫婦間、親子間での扶養の範囲にあたるものは特別の寄与にはあたりません。
特別の寄与をした相続人には、まず寄与分を渡し、残りの財産を共同相続人で分割することになります。
民法の改正(2019年7月1日施行)により相続人以外の親族も寄与分の請求ができるようになりました。
詳しくは特別の寄与の制度
特別の寄与になるもの
- 事業に関する労務の提供または財産の給付
たとえば、会社を経営する父のもとで長年無償で働いていた。
- 被相続人の療養看護
たとえば、自ら看護をすることにより人を雇う経費を削減した。
- その他の方法により被相続人の財産の維持、増加に貢献
たとえば、父の会社に資金の援助をした。
相続分の計算
相続人が3人(妻、長男、長女)、相続財産が10000万円で長男に2000万円の寄与分がある場合
10000万円(相続開始時の財産)-2000万円(寄与分)=8000万円
妻(相続分2分の1)
8000万円×2分の1=4000万円
長男(相続分4分の1)
8000万円×4分の1=2000万円
2000万円+2000万円(寄与分)=4000万円
長女(相続分4分の1)
8000万円×4分の1=2000万円
となります。